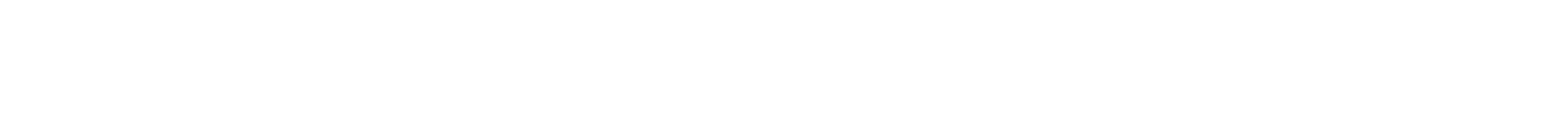秀島菜々子
最近、本屋の中が血の海に見える。
私が若いうちから耄碌しているのかもしれない。しかし生憎、身体そのものは正常だ。ならば身体以外の私を形作るものが以前とは変わったということになる。
それは意識だ。
二一歳、大学三年生。この要素を踏まえた人間が見据える道標の最たるものは就職だ。就職、すなわち就活。私は「編集者になる」夢を叶えるために大学へ入学し、邁進してきたわけだが、ついに手に届くチャンスにまみえるラインに立っているのだ。
同時に夢だと思っていたものが現実としてあらわれる慄きを体感することになる。
徐々に現実を知るごとに、自分が勝手に描いていた理想とのギャップに辟易してくることも少なくない。
作家たちは自らの手で命を一枚一枚剥ぐように営々と物語を綴っている。そしてまた、編集者たちも血豆を潰すように作家の創作物を共に鍛えている。その努力の果てにようやく一冊の本が売られているのだと、ようやく知る。
今まで楽園だと思っていた本が人々の血肉を削ぐように作られたものなのだと。
私は本屋巡りが好きだ。本が並んでいる場所に向き合うと、自分の中で枯れて萎れていた苗木に水が与えられ、根が吸い込み、みるみるうちに若返っていくのを感じる。その場に立っているだけで呼吸がしやすくなった気さえする。本棚は私の生命の源なのだ。
しかし、ひとたび裏側を知ってしまえば、爽やかな雰囲気を醸していたそこはある時を境に重苦しい空気を纏うようになった。本棚に目を通せば息が吸いにくくなり、本に触れれば胸が締め付けられる。体感した最初こそ無自覚だったが、自覚してから原因を突き止めるまではすぐだった。夢が現実になりうるグロテスクを薄々感じ取っていたからだろう。
何も知らずにただ己の快楽に変換して貪っていたあの頃にはもう戻れない。
後ろを振り返ることしかできなくなり、静かに枕を濡らした日もある。あの頃の幸せをもう一度掴むために考えることをを放棄したこともある。それでも、「もう戻れない」という一種の清々しさからは逃れられなかった。
私はそれでも本に携わりたい。今持てる全てをかけて夢を現実にしたい。私のこれからの人生は全く想像もつかない世界が待っているだろう。自分はこの血の海に飛び込んで世界を泳いでいくのだ。