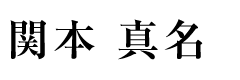鏡のなかの鏡
ミヒャエル・エンデ 著/丘沢静也 訳
岩波書店/1984年
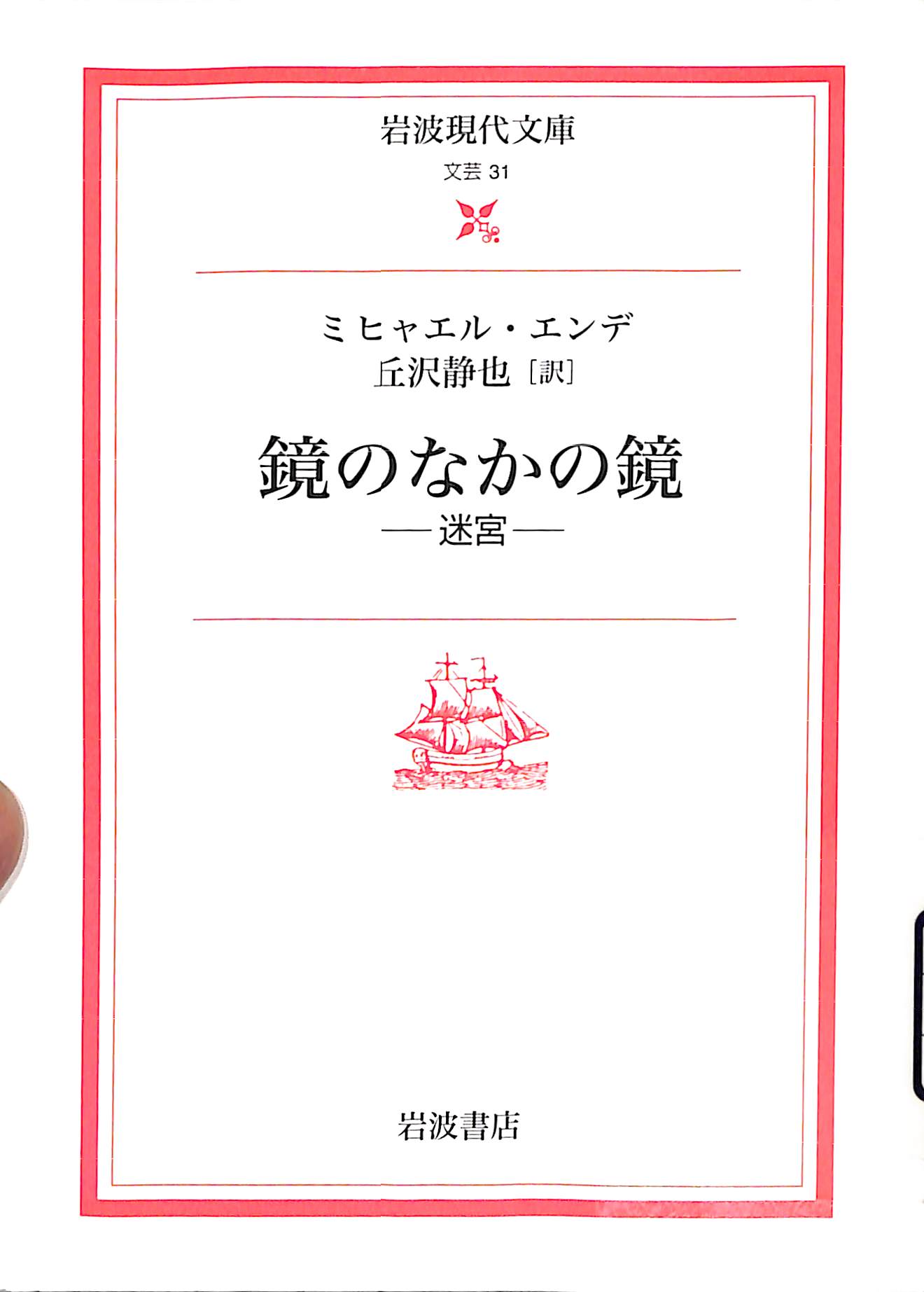
-
この本を開いて私はこの世界の美しさに感嘆の息が漏れた。
全世界の人が美しい世界だと言うのかは分からないが、私は確かにこの世で美しくそしてどこか空虚で幻のように幻想的な世界に魅了されたのだ。鏡のなかの鏡は短編小説だ。
いくつもの短編小説は内容面ではどこもつながっていないように見えるが最後の一つの要素と次の世界の始まりは少しだけ似通っているのだ。
その少しのつながりは鏡を現した「鏡」と表現している。
鏡のなかの鏡はこうも変わってしまうのだ、と。
その点だけ見てもかなり他の作品にはない特殊な作りとなっている。
だが重要なのは中身だ。
短編の一つ一つの内容はどれも非現実めいている。
どれもこれもどこかおかしく中々想像しづらいと感じてしまう。正直言葉の暴力と言っても過言ではない。
辻褄があっているのかも分からない。
それだけれど、文字の内容から全ての要素を掬い出して想像できる世界は独特の空気感とここでしか見えない景色があった。何故こんなにも美しく怪しい物語が書けるのか、疑問は絶えず自分を襲った。
そして、考え、自分で文章を書き写したりしているうちに、疑問は魅了に変わり、自分はさらにこの異質で理解の範疇を超えた世界に酔心していった。この物語はどことなく、「何か」に似ていた。
起承転結がなく、それでいて時に美しく、時に恐ろしい。
そんな、誰でも知っているであろう「何か」にだ。そう、そうだ、ああ、ああ!
思い出した、これは夢だ。
無意識の内に見るであろう、夢なのだ。
であるならば、この物語たちは著者の夢なのかもしれない
私達は彼の夢を覗いているのだ。
この本に書かれている物語は全て夢なのだ!
夢と言うのは物語としては到底、語れるほどの起承転結も設定も曖昧であることが多々ある。
だからこそ、夢の性質を前面に押し出している。
まるで起きているのに眠って他人の夢を覗くような気分に浸れること間違いなしだ。ぜひ、眠る前のお供として読むことを私はお勧めする。
この本はきっとあなたを夢の世界に連れ去ってくれることだろう。

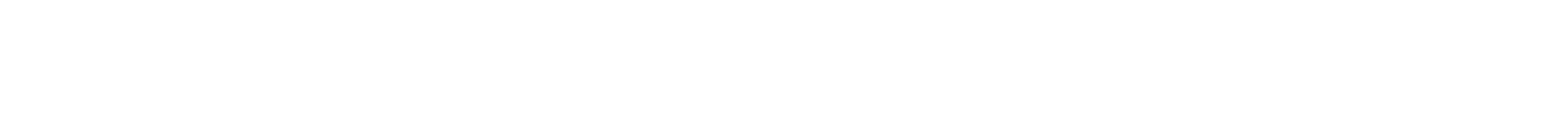
読み手: